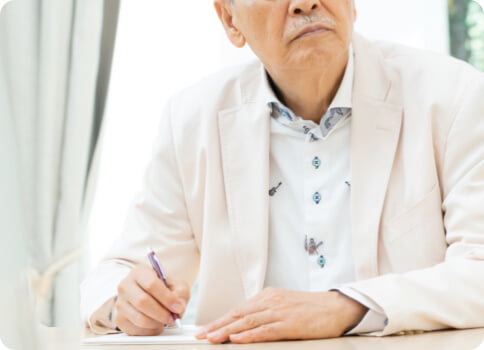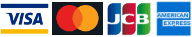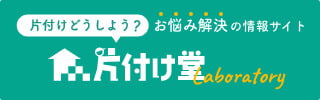葬儀や法要と違い、これといった期日が決まっていないのが遺品整理です。いつから遺品整理を始めて、いつまでに何を終わらせればよいのでしょうか。この記事では一軒家や賃貸物件などの具体的な事例も交えながら、遺品整理の時期やコツを解説します。遺品整理のタイミングや手順のポイントを知って、故人の遺志に叶った、ご遺族の負担が少ない遺品整理をしていきましょう。
そもそも遺品整理とは?
遺品整理とは、親族や身内がなくなった際にその人が使っていたものを整理し、相続や形見分け、処分などを行うことです。遺品処理、遺品処分とも呼ばれます。
遺品整理は土地や家、車などから日頃使っていた万年筆、貴金属など広範囲に及びます。また、手紙やアルバムなどの第三者からは値段が付けられないものも対象です。近年ではデジタル写真やSNSアカウントなどの「デジタル遺品」も遺品として扱われるようになりました。
遺品整理はいつからでも大丈夫
遺品整理は法律上「いつまでにしなければならない」という決まりはありません。
ただし、預貯金や有価証券、不動産、貴金属など相続税の対象となるものは、納税期限があります。また、医療保険や年金、借金なども、早めに手続きを早めにするべきです。
賃貸契約もそのままにしておけば家賃がかかります。また、社宅や公営住宅、高齢者施設などでは、退去期限が決まっていることがあるので注意が必要です。
親族が集まれる日時の都合を計画しておき、余裕を持って適切なタイミングで遺品整理をしていきましょう。
遺品整理を長引かせると生じるリスク
遺品整理を長引かせると、心身に負担がかかり金銭的な負担も大きくなるリスクがあります。
親しい人が亡くなったことで精神的に落ち込むなどして、遺産整理を放置してしまう人がいます。しかし、先延ばしにすると、遺品を捨てられなくなったり、整理が面倒になったりしてしまう人も少なくありません。
また、忙しいので少しずつ遺品整理を進めようとして、家賃や故人の家への交通費など追加費用が発生してしまうこともあります。
遺品整理を始める際には、計画的に終わらせましょう。特に使用する予定がないものは、早めに処分しておくことが重要です。
遺品整理はいつから?|4つのタイミング
遺品整理を始めるタイミングはいつがよいのでしょうか。ここでは四十九日法要後、葬儀直後、さまざまな手続きの完了後、10カ月以内の4つを解説します。
葬儀を行うのが初めてで何から手を付ければ良いのかわからないという方も多いかもしれません。
そのような場合、こちらのサイトでわかりやすく説明をしてくれていますので是非参考にしてみてください。
葬儀・お葬式は信頼の葬儀社|公益社
タイミング1.四十九日法要後
命日から数えて49日目の日の「四十九日」を目安に遺品整理を行う人は多くいます。仏教において故人の来世での行先が決まり、魂が次の世へ旅立ったということで、遺品整理をしやすくなるからでしょう。
四十九日法要は親族や関係者が集まる日でもあり、このタイミングで形見分けを行いやすいメリットもあります。
タイミング2.葬儀直後
葬儀直後は遺品整理にスピードが要求される場合に向いています。相続権がある親族が集まるため、相続に関係した遺産整理を話し合って決められます。また、賃貸物件に住んでいた場合は、大勢で片づけを行い、形見分けや不要なものの処分を手早く行うことも可能です。
ただ、前もって段取りを伝えておかなければ、親族や身内の都合が付かないことも少なくありません。
タイミング3.さまざまな手続きの完了後
さまざまな手続きがひと段落してから遺品整理を行うことは、心身に負担が少ない方法の1つです。
葬儀や法要、死亡届の提出、年金・保険金の手続きなど、故人が亡くなった後しばらくは何かと忙しいものです。また、電気・水道・ガスなど公共料金の解約や月額利用料の発生するサービスの解約などもあります。
遺品整理前の手続きを確実に終わらせておきたい人や、じっくり遺産整理に取り組みたい人に向く方法です。
タイミング4.10ヵ月以内
相続税の課税基準日から逆算して遺品整理を進める人もいます。被相続人(故人)が亡くなり相続権が発生してから、10カ月以内に相続の申告書を提出しなければなりません。
申請期間を過ぎると、相続税の控除を受けられなくなり、延滞税を課されてしまう場合もあるので注意が必要です。特に相続する資産が多い場合は、10カ月以内のリミットを意識して遺品整理をスタートさせましょう。